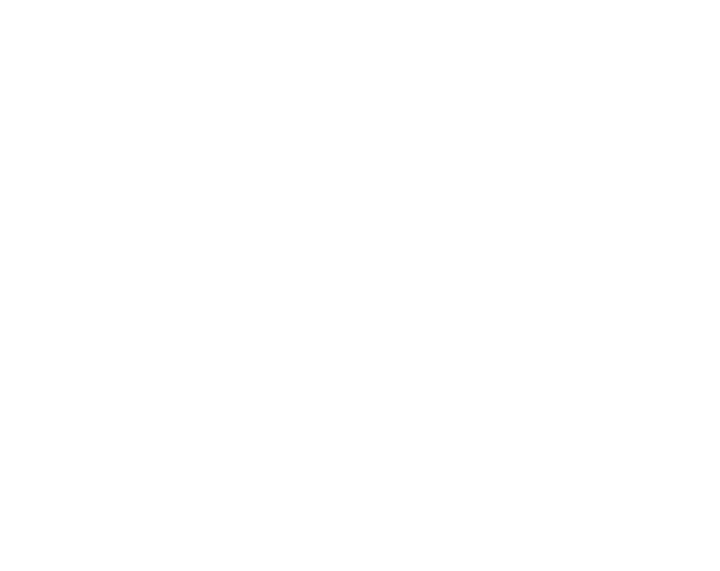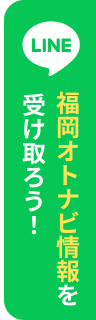令和7年2月1日(土)、福岡100プラザ東において約70名が参加の「初春のお茶会」というイベントが開催され、福岡オトナビが取材・インタビューに伺いました。
このイベントは、東区にお住まいの男性から、お母さまが生前愛用していた「立礼卓(りゅうれいじょく)」を、福岡100プラザ東に寄贈されたことがきっかけとなり、開催されたものです。
そこで今回は、その「一期一会」を大切に、みなさんに是非楽しんでいただきたいと、シニア教室で講座を持たれている茶道教室の太田ヨシヱ先生と、三味線教室の青山舟月(せいざんしゅうげつ)先生の初コラボでイベント企画が実現しました。

茶道と三味線を組み合わせた特別なイベントが実現
今回初めての試みとなるこのイベントは、第1部「三味線鑑賞とお茶のお点前の披露」と、第2部に、みなさんが参加できる「お茶会」を催すという流れで進行しました。
まずは冒頭でのご挨拶とともに、日本の茶道の歴史やお茶の作法について、先生お2人からお話をいただきました。
その内容は、日本の茶祖と呼ばれる臨済宗の僧・栄西が中国からお茶の種を持ち帰り、日本で栽培を始めたことや、500年前には豊臣秀吉が九州でお茶会を開いていた、という歴史の話や、茶道における「三千家(さんせんけ)」の称である表千家・裏千家・武者小路千家の違いやお茶の基本作法のお話など、あらためて日本文化の奥深さに気づかされる内容でした。
そして、いよいよ舞台の上に再現された「茶会」で、三味線とお茶のお点前がコラボレーションした演目が繰り広げられました。 美しく強い三味線の音色と唄と語りに導かれるように、また導くようにお茶のお点前が披露され、日本ならではの作法の美しさが際立つ、素晴らしい内容に会場の皆さんも聴き惚れ、見惚れながら、静寂の中の時間を楽しまれていました。

「少し緊張しますね」と笑顔で。美味しいお茶とお菓子とともに
第2部では、大広間に置かれた数か所のお茶席で、イベントに参加されたみなさん全員が、お待ちかねのお茶会に参加をしました。
もちろん、寄贈された「立礼卓(りゅうれいじょく)」の席でも、本格的なお茶をいただくことができました。
それぞれの場所で、自分のお点前の順番が近づいてくると、参加されたみなさんは、自然と背筋がピンとし、程よい緊張感がありながらも美味しいお茶とお菓子をいただいていました。


※写真 「立礼卓(りゅうれいじょく)」 |

|
茶道と三味線の出会い。偶然が生んだ美しい伝統文化のコラボレーション
今回の特別なイベントは茶道と三味線、異なる伝統文化が融合し、参加者に新たな感動を与えました。
この企画の中心となったのは、茶道講師の太田ヨシヱ先生と三味線講師の青山舟月先生で、この「一期一会」となる素晴らしい出会いについて、イベント終了後お話をお伺いしました。
「もともと私は青山先生の『月琴と語り』のライブをよく観に行っていました。とても素晴らしい演奏で、すぐにファンになりましたね。ある日、共通の知人を通じて紹介してもらい、話をしているうちに青山先生から「一緒に何かやりませんか?」と。
それに対し、太田先生が「面白そうですね!」と即決でした。初めての試みでしたが、お茶の作法と三味線の音色が自然と溶け合い、とても美しい空間が生まれました。」と笑顔でお話をされました。
そして驚くことに、このコラボレーションは、リハーサルや入念な打ち合わせを数回しか行わず、即興で実施されたとのこと。それにもかかわらず、まるで長年の演出のような完成度の高い舞台となり、観客を魅了したことに驚きを隠せませんでした。
伝統を守りながらも「楽しく」。共通するお2人の指導方針
福岡100プラザ東では、シニア世代の方々が生きがいを持って学び、楽しむ場を提供しています。その中で、茶道と三味線の教室も多くの方が参加し、日々の活動をされ、講師のお2人も教室の生徒さんとコミュニケーションをとりながら、熱意とポリシーをもって教室運営をされています。
「私の教室では『楽しいことしかしません!』と決めています。茶道は静寂の中で行うものと思われがちですが、私の教室では皆さん笑いながらお茶を楽しんでいます。」と太田先生。
それに対し、青山先生も「音楽も同じです。楽しくないと続きません。無理にやらせることはせず、まずは楽しんでもらうことを第一に考えています。」とお話になり、その言葉にお互いが大きく頷かれていました。
お2人の共通のポリシーは、「伝統を大切にしつつ、楽しむことを最優先にする」という点で、厳格な作法にとらわれすぎるのではなく、誰もが気軽に参加し、心豊かになれる場を作ることが目標だと語ります。今回のイベントは、教室で生徒さんと触れ合いながら、毎日をイキイキと過ごすための楽しい場づくりを、お2人が最優先に考えていることから実現したものだと感じました。

※三味線 青山舟月先生(写真左)、茶道 太田ヨシヱ先生(写真右)
日本の伝統文化の未来を考える。 継承と新たな挑戦に向かって
現在、日本の伝統文化を継承する人が減少しつつあります。茶道においては、かつて習っていた経験のある人が多いものの、長く続ける人は少なくなってきているのが現状だということです。
「最近は『正座ができないけれど、茶道を習いたい』という方が増えています。
私の教室では、正座が難しい方のために、椅子を使ってお稽古をしています。どんな人でも茶道を楽しめるようにしたいですね。」と太田先生は語られ、同じく青山先生も「三味線も同じです。『難しそう』というイメージがありますが、実際にやってみると、意外と楽しいものです。初心者の方でも、まずは触れてみることが大切ですね。」と話されました。
また、そんなお2人は伝統文化の継承において、今後の活動についても意欲的です。
「もっと地域の皆さんと一緒に楽しめる機会を増やしたいですね。
例えば、『餅つきと三味線のコラボ』をやってみたいです。昔、博多では餅つきをする時に太鼓や三味線が演奏されていたんですよ。」と青山先生がお話されると、太田先生がすかさず「それ、いいですね!あとは博多どんたくのように、町を流しながら演奏するのも面白いかもしれませんね。」と嬉しそうに話され、お2人の言葉から伝統を守るだけでなく、新しい形で伝え続けることの大切さを教えられました。
最後に 一期一会の精神
今回のコラボレーションのテーマは「一期一会」。一期一会の語源は「茶会に臨む際は、その機会を一生に一度のものと心得て、主客とともに互いに誠意を尽くす」というもの。戦国時代、武将たちは戦に向かう前にお茶を飲み、一瞬一瞬を大切にしました。そしてこの精神は、現代にも通じるものです。
「今日という日は二度と来ません。だからこそ、一つ一つの出会いを大切にしたい。」と太田先生は話され、「お客様が『素敵だった』『感動した』と言ってくれることが、何よりの喜びです。」と青山先生は力強い言葉で語られました。
伝統文化は「堅苦しいもの」と思われがちですが、実際には「楽しく、美しく、人と人を繋ぐもの」。お2人の活動を通じて、その魅力がより多くの人に伝わり、今回の福岡100プラザ東で行われた初のイベントの試みが、大きな流れとなることを期待しました。
また、今回の取材のように、福岡オトナビでは社会参加のステップアップ支援をしておりますの で、是非お気軽にコーディネーターにご相談ください。

※写真 茶道教室(太田ヨシヱ先生と生徒の皆さん)、三味線教室(青山舟月先生)