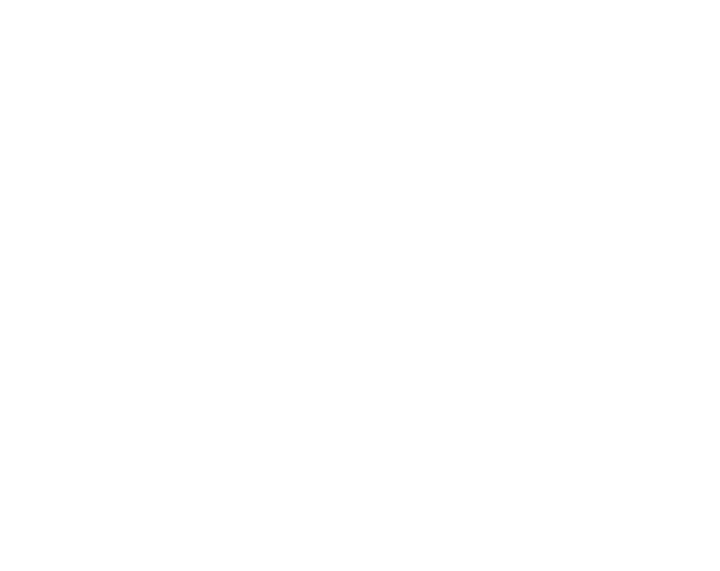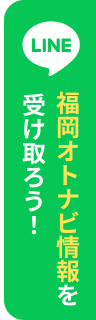「笑いは脳トレですよ。」
そう語るのは、長年にわたり多くの人々を楽しませ続ける落語家・笑っ亭風太郎氏。
「笑い」をただの娯楽ではなく、心と体を健康にする不可欠な要素と捉えています。
「笑うことは、人と人との間にある垣根を取り払い、お互いの相対する笑いが、自分と相手の心と脳のストレッチをする。
いわゆる脳のトレーニングにつながっているんです。」と、優しく柔和な笑顔でインタビューに答えていただきました。

人生に生き続ける落語と、世代間にある「笑い」の捉え方とは?
落語という伝統芸能は、日本文化の一つとして400年以上の歴史を持ち、特に言葉遊びや語彙力がその魅力の中心にあるとのことですが、若者とシニア世代では笑いの感じ方が大きく異なるといいます。
「若い人は、派手な動きや視覚的なインパクトに笑いを感じやすい傾向にありますね。例えば漫才とかお好きな方が多い。しかし一方でシニア世代は、これまでの人生経験を通じて蓄積された言葉への感度が高いので、落語の言葉遊びにより強く反応するんです」と風太郎氏は語ります。
また「言語能力は80歳頃まで伸び続けるとされています。それは落語にとって、とても良い土壌でもあるし、長い年月がたっても話芸として愛され続ける由縁であると思います。」とのこと。
この言葉から、落語が単なる娯楽ではなく、人間の言語能力を刺激する芸術として、人々の人生や暮らしの中に生き続け、その礎となってきたことに気づかされ、深く感銘をしました。
「完全懲悪」がなく、生活や人間関係の共感から生まれる落語の面白さ
「実は落語の登場人物は、みんな少し抜けていたり、ドジだったりするんです。そうしたキャラクターが織りなす会話が、観客の共感を呼ぶんですね。浪曲や講談のように強い人間やヒーローが登場するというより、自分たちの身近にいるような人々が主人公なんです。」と語る風太郎氏。
これは、現代の社会にも通じるものがあり、必ずしも大きな成功や完璧さを求めるのではなく、失敗や不器用さの中にこそ共感があり人生があるという落語の哲学が、多くの観客に受け入れられている理由の一つだと気づかされます。
また落語の即興性と観客とのインタラクティブ(双方向性)なライブ感が楽しめるのも落語の魅力のひとつです。
落語には「つかみ」や「枕(まくら)」と呼ばれる部分があり、これが観客の心を掴む鍵になるとのこと。
「最初にいかに観客に興味を持ってもらうかが重要です。そのためには、場所や観客の年齢層、雰囲気に合わせてネタをアレンジする柔軟性が求められますね。」
風太郎氏は公演の直前に観客を見て、その日のネタを変更することもあるといいます。「直感で『これを話したらウケるかな』と判断してネタを足したり引いたりする。これが落語家としての醍醐味でもあり腕の見せ所でもあります。」
お客の反応を見ながら、双方向的な笑いの空間を作り、落語の面白さと同時に共感の輪を作り出す。同じネタであっても、明日はまた違う笑いが起こっている。
即興性でありながらも観客を見事に「笑い」の世界に連れていく、究極のライブ感を味わえる落語の魅力に、あらためて気づかされました。
働きながらの落語活動が、たくさんの出会いを生み社会参加につながる
製薬会社に入社し営業マンとして得意の話術で成績をあげる一方、「健康」に関する医学・薬学の知識を学び、人の免疫力や病気を治す力に「こころ」の影響が大きいこと、「笑い」の重要性を学んだ風太郎氏。
後に【日本笑い学会】会員として、多くの研究や論文を発表し、多方面で活躍されてきました。
現代社会において、仕事をしながら芸事を両立するのは容易ではない一方、働きながらこそ見える景色や得られる発想も、落語活動に深く影響してきたと思います。
そして、落語が単なる活動ではなく、生きがいそのものであり、覚悟と使命感もって挑んでいることが、言葉の節々に表れます。
また、風太郎氏は「笑いは人間関係を築くための技術でもあり、社会参加に不安を感じる人や人間関係に悩む人にとって、大きな助けになると思います。」と強調し、
「落語の中の登場人物は、みんな弱点を持った普通の人間です。そうしたキャラクターが織りなす物語に触れることで、観客は自分自身の姿を重ね、安心感を得ることができるんです。」と語ってくれました。
風太郎氏の言葉には、笑いが人生を豊かにするものであるという信念が込められ、さまざまな困難にぶつかっても、「笑うこと」は人生を明るくする力を持っている。
風太郎氏の語りは、私たちに「自分らしい笑い」を見つけるヒントを与えてくれたように思えました。
(令和6年 12月22日 福岡プラザ西にてインタビュー)